vol.25
進化続ける健康経営のカタチ
時代に合わせた継続的実践を
経済産業省が健康経営優良法人認定制度を創設してから10年。「従業員の健康維持・増進への取り組みが、結果的に生産性や企業価値の向上につながる」という考え方が浸透し、健康経営を実践する企業も年々増加しています。社会情勢の変化が加速する中、健康経営のとらえ方はどう変わってきたでしょうか。近年の潮流と今後の方向性を聞きました。
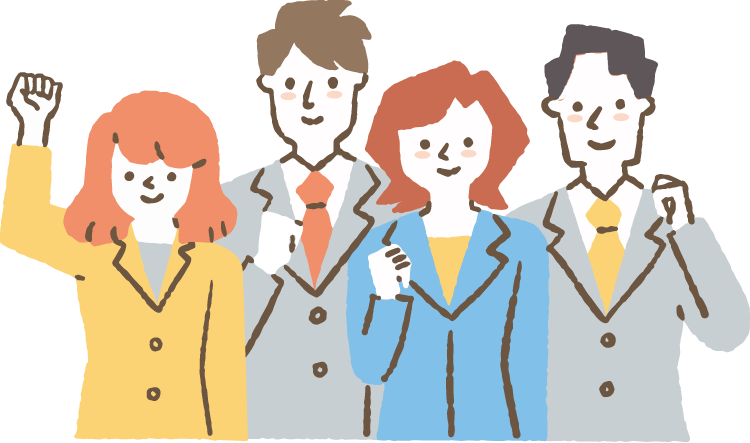

女性の健康課題を理解し、
誰もが働きやすい社会へ
東北大学 名誉教授
同大学院医学系研究科
公衆衛生学 客員教授
辻󠄀 一郎 氏
女性の社会進出が進み、女性を含めたすべての人が働きやすい職場づくりは、企業の重要な課題となっています。女性特有の健康課題とはどのようなもので、企業はどう取り組むべきでしょうか。公衆衛生学の専門家、東北大学名誉教授・同大学院医学系研究科公衆衛生学客員教授の辻一郎氏に、健康経営の視点から解説していただきました。
20~50代に現れる
女性特有の健康課題
健康経営は、戦略的に従業員の健康管理を行う取り組みです。法定事項やコンプライアンスの範ちゅうにとどまらず、より踏み込んで投資を行う点がポイントで、全国的にも宮城県内でも関心が高まっています。背景には、経済産業省などがけん引する健康経営優良法人認定制度があります。この認定を受けることで自社のイメージアップにつながるだけでなく、実際に人材確保や離職率低減、生産性向上など具体的なメリットを実感する企業が増えています。
健康経営の概念が浸透する中、近年特に女性に対する健康支援が注目を集めています。昨年2月、経済産業省は女性特有の健康課題による社会全体の経済損失を年間約3・4兆円と推計しました。相当インパクトのある数字です。健康経営優良法人の認定要件にも、女性特有の健康課題への対応に関して具体的な質問が盛り込まれています。
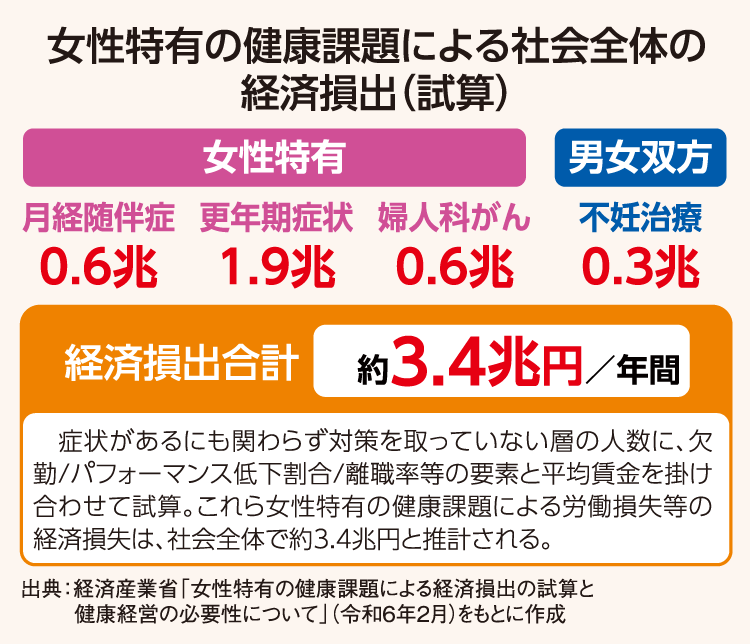
働く女性が増え、日本の労働力人口に占める女性の割合は45・1%(2023年)まで上昇している一方、上場企業の役員に占める女性の割合は10・6%(同年)。このギャップは、いまだ男性社会の中で女性が孤立していることを表しています。また、女性特有の健康課題は多様ですが、問題はそれらが20~50代の働く世代に多く現れること。ライフステージごとにさまざまな症状や病気が出現し、仕事に影響を与えています。逆に考えると、女性の健康課題に的確に対応することで、企業全体の生産性を大きく改善できるといえます。
理解深め具体的な対応を
コストかけない工夫も
取り組みのポイントは「理解の促進」「組織体制の整備」「積極投資」の三本柱です。職場での理解を進めるには、ヘルスリテラシーの向上プログラムや管理者向けコミュニケーション研修を実施するなど、会社全体で課題意識を共有すること。経営トップが社内へメッセージを発信することも効果的です。組織体制に関しては、女性管理職の登用拡大・採用時の平等についての具体的な目標設定や、女性が相談しやすい体制の整備から取り組むといいでしょう。投資の実際の事例としては、外部リソースを活用した相談会や健康支援の実施、検診・通院の費用補助、社内で婦人科診療の提供などがあります。中小企業でも、気軽な相談グループの立ち上げや、外部の無料講座への参加と知見共有など、コストをかけずに工夫して取り組む企業も増えています。
女性に優しく、
全ての人が働きやすい職場へ
女性の健康支援に絞って話しましたが、実際の内容は、個別の健康課題に応じた柔軟な雇用状況を作るという「インクルージョン&ダイバーシティ」の概念そのものです。女性に優しい環境を整えることで、男性も自然に働きやすくなる。会社全体を根本的に変えることができれば、今後起こりうる産業構造の変化や外国人労働者の増加などにもスムーズに対応できるでしょう。
政府は「女性版骨太の方針2025」の中で、女性に選ばれる地方づくりが急務と強調しています。地方が選ばれるためには、魅力ある企業・産業の存在が不可欠。超売り手市場が続く中、健康経営の実施は求職者に選ばれる指標の一つです。私は健康経営に積極的な企業をいくつも見てきましたが、いずれも和気あいあいと明るく、社内コミュニケーションが円滑な印象。選ばれる企業、選ばれる地域づくりのためにも、多くの企業に健康経営に取り組んでほしいと思います。
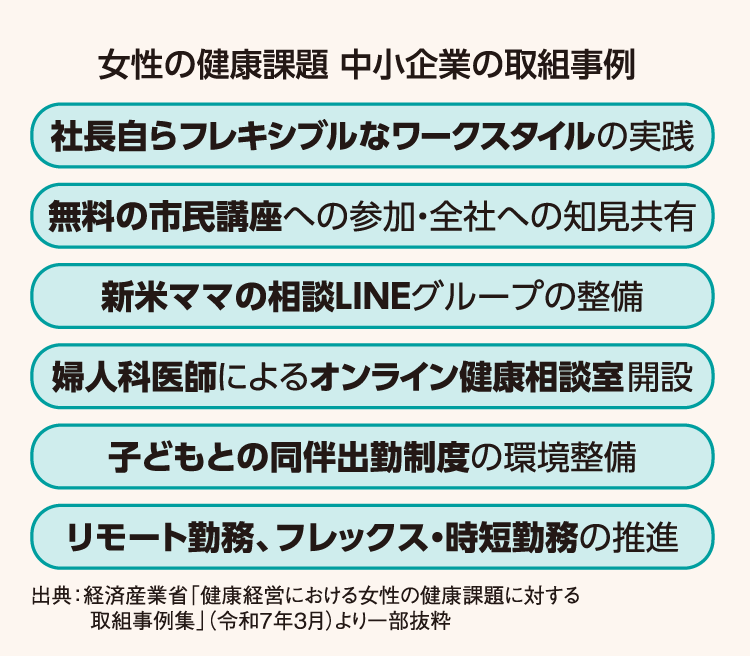

企業ごとに最適な健康経営を
健康経営優良法人
認定事務局
清水 桃子 さん

健康経営優良法人認定制度が2016年度に始まってから、認定件数は右肩上がりに増加しています。今年度の申請スタートを前に、ポータルサイト「ACTION!健康経営」での情報発信や、認定制度の申請窓口を担う、健康経営優良法人認定事務局の清水桃子さんに昨今の状況や今後の展望を聞きました。
よりよい職場づくりに
健康経営の活用を
今年3月に発表された「健康経営優良法人2025」には、大規模法人部門に3400法人、中小規模法人部門に1万9796法人が認定されました。上位500法人に付加される「ホワイト500」(大規模)、「ブライト500」(中小規模)に加えて、新たに中小規模法人部門に「ネクストブライト1000」の枠が設けられました。中小企業の積極的な取り組みが増加するなか、通常認定からブライト500を目指すためのステップとして位置づけられています。
近年の潮流として、単に従業員の健康管理だけでなく、それぞれの経営課題に応じた目標設定や施策が実施される傾向があげられます。業務改善のサイクルに健康経営の概念を取り入れ、よりよい職場づくりのために上手に活用する動きが増えています。また、個々の従業員の健康状態に即して先進的な取り組みを行う企業も見られるようになりました。
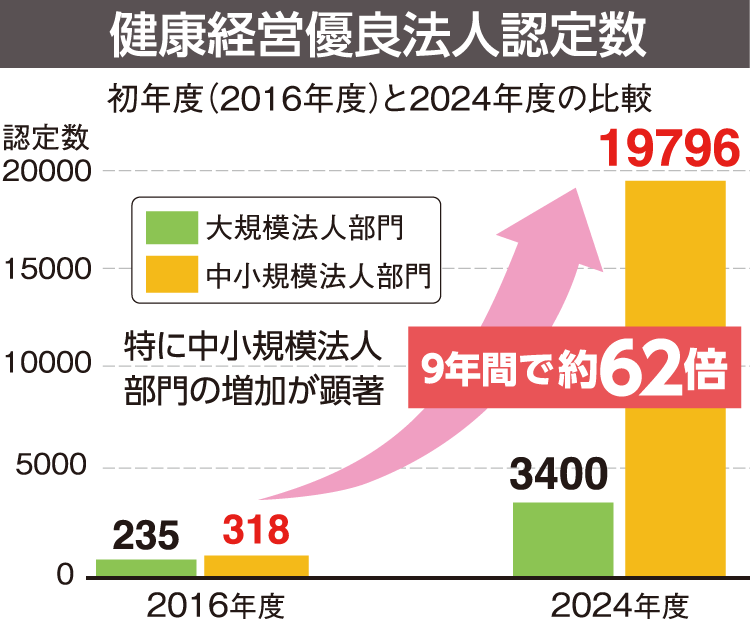
トレンドは「人にフォーカス」
調査票の内容にも変化
これからの健康経営のポイントを三つあげたいと思います。一つ目は「人にフォーカスした施策」。働き方改革、人的資本経営など、人材をより重要な資産として捉える考え方が広まり、健康経営度調査票や申請書の内容もその流れを取り入れて変化しています。二つ目は「経営層の積極的な関与」。経営トップが自ら旗振り役となり方向性を示すことで、組織全体への意識付けが大きく推進されます。三つ目は「女性の健康支援」。女性特有の健康課題はセンシティブな内容を含むこともあってか、実際のニーズに応えられていないケースが少なくありません。制度を作るだけでなく、実効性が増すように職場全体のリテラシー向上が不可欠です。
企業の課題は一社ごとに異なります。先進的な事例や他社のアイデアは参考になりますが、そのまま取り入れて自社に合うとは限りません。社内のニーズを把握し、必要な施策を打っていただきたいと思います。
信頼の指標としての認定
「優良法人」にチャレンジを
健康経営優良法人の認定件数は年々増加しているものの、企業全体の母数を考えればまだまだ浸透の余地があります。事務局では、健康経営の概念を企業だけでなく社会全体に根差したものにするべく、普及と拡大に取り組んでいます。
「関心はあるが実際に取り組むのは大変そうだ」と二の足を踏む企業もありますが、普段からコンプライアンスを遵守していれば、それほどハードルが高いことではありません。健康経営の実践は「従業員を大切に考えている」という企業の明確なメッセージ。人材面の課題に対するソリューションの一つになります。求職者はもちろん、投資家や地域社会、取引先などからの信頼と評価を高めるといったメリットもあります。
より多くの企業に理解を深めてもらうため、事務局では健康経営の意義や実施手法を分かりやすく解説したハンドブックを今年度発行する予定です。ポータルサイト「ACTION!健康経営」では最新情報や役立つコンテンツを随時更新していますのでぜひ参考にしてください。
2025年7月28日付 河北新報朝刊_特集紙面 Vol.25より転載
特集紙面の
PDFダウンロードはこちら
このページの内容は河北新報に掲載された特集紙面を一部再編集してご紹介しています。
河北新報掲載の特集紙面は以下よりダウンロードできます。

